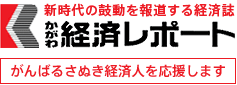10月25日号

建ロボテック㈱(三木町 眞部達也代表取締役社長兼CEO)はこの度、国土交通省、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、(一社)日本機械工業連合会共催の「第11回ロボット大賞」の国土交通大臣賞を受賞。10月7日に池田豊人知事に受賞報告をおこなった。
「ロボット大賞」は、国内のロボット技術の発展や社会実装を促進することを目的として、ロボットの先進的な活用や研究開発、人材育成といった様々な分野において、優れた取り組みを実装した企業等を表彰する制度で、今回が11回目の開催となる。
同社は2013年設立以来、「世界一ひとにやさしい現場を創る」という事業ミッションを掲げ、建設現場の課題を解決する省力化・省人化ロボットを開発・提供するベンチャー企業。昨今の建設従事者の減少など、業界の課題解決に取り組んでいる。
今回、受賞となった「鉄筋結束トモロボ(以下:トモロボ)」は、同社が令和2年に製品化した鉄筋を自動結束する高機能ロボット。